- Question
-
どうしたら、パナソニックならではの表現で、目指す未来のビジョンを語り、社内外の多くの仲間を巻き込むことができるだろうか?
パナソニックが、2040年の未来にありたい姿とその実現に向けた研究開発の方向性を示した「技術未来ビジョン」。そのビジョンを社内外に伝え、多くの人を巻き込んでいくためのストーリーテリングをKESIKIが伴走しました。
2040年の未来。気候変動や資源枯渇、少子高齢化などによって、資源や働き手が減り、これまでの社会システムでは立ち行かなくなってしまうのではないか。そんなシナリオを描く中で注目したのが「共助」という考え方でした。
たとえば、それぞれの家やオフィスで自家発電した電力を分け合う。壊れてしまった製品を修理できる人に直してもらい、大切に使い続ける。限りあるリソースから、できる限り多くの価値を生み出せるようにする。そんな「共助」が自然とめぐるシステムをつくりたい。それがこれからのパナソニックの使命なのではないかと考えたのです。
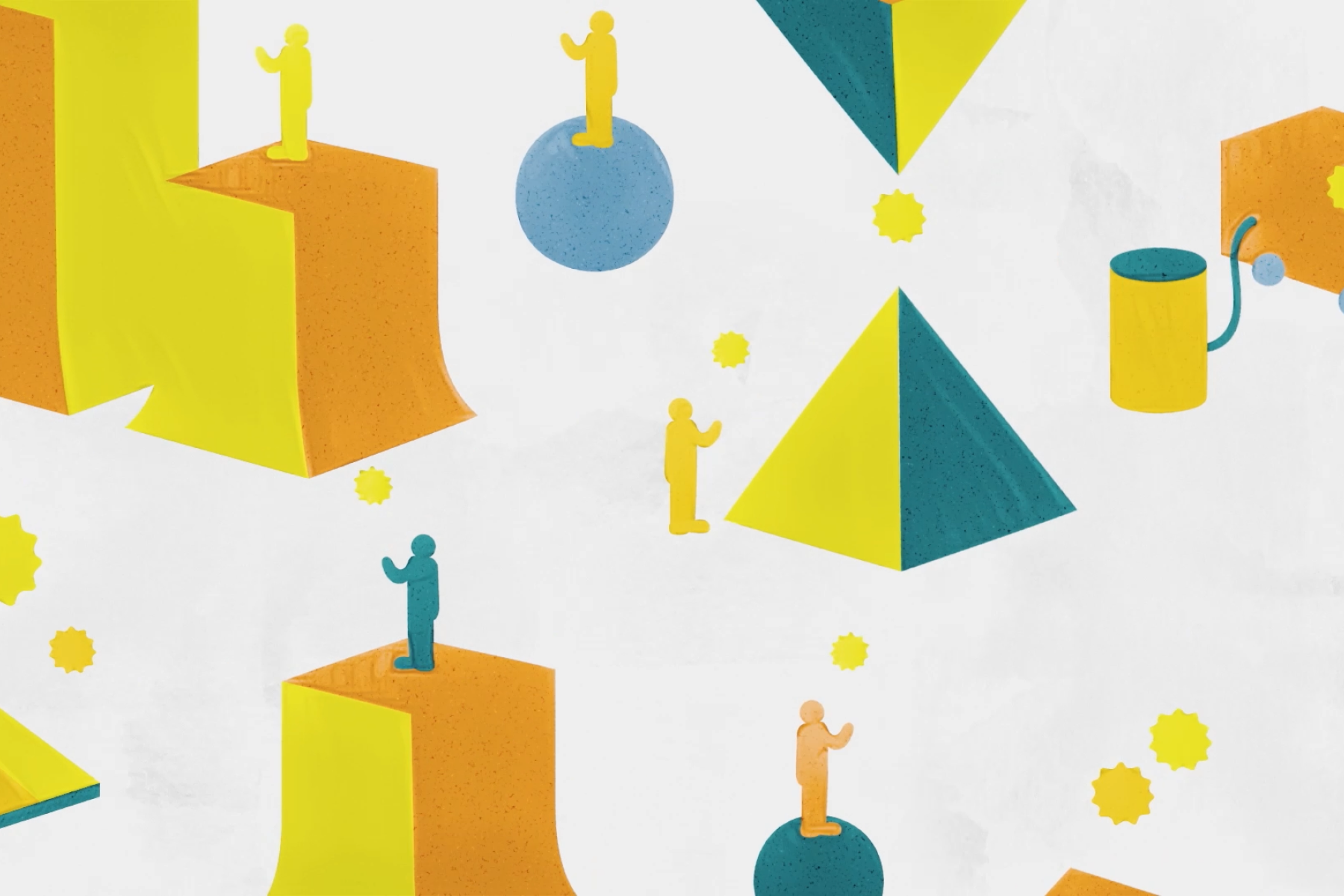
ストーリーを設計していくにあたって、まず、ターゲットのインサイトや、このメッセージを受け取ってどんな行動を取ってほしいのかというジャーニーを考えていきます。
ひとつの大きな課題は「共助」という言葉が、意識が高いように思えてしまうことでした。どうしても「自分のことだけでも精一杯なのに誰かを助けるなんて無理」「みんなで助け合いを目指そうなんて偽善的なのでは」という印象を持たれかねません。
強調したいのは、それぞれの個人や企業が持つスキルや時間を、適切にマッチングさせて再分配することで、自分も得をしながら、誰かを助けることができる、ということ。そして、その循環によって、社会全体の様々な課題が解決していくということ。
そのことが分かりやすく伝わるような表現を考え続け、「一人ひとりの選択が自然に思いやりへとつながる社会」というビジョンワードに辿り着きました。
また、ムービーの方では、実感と共感が湧くよう、できる限り具体的な事例を描き、生活者目線でストーリーを語っていく流れに。インサイトを意識しながら、コピーライティングとムービーの制作を進めていきました。

ストーリーテリングにあたって、もう一つクリアしなければならない課題が。「なぜ突然電機メーカーのパナソニックがそんなことを言いはじめたの?」という疑問を解消することです。
そこで改めて、なぜパナソニックがこのビジョンを実現させたいのか?を振り返ってみると、根底には創業者である松下幸之助が1930年ごろに唱えた「水道哲学」があるという意見がチーム内で出てきました。
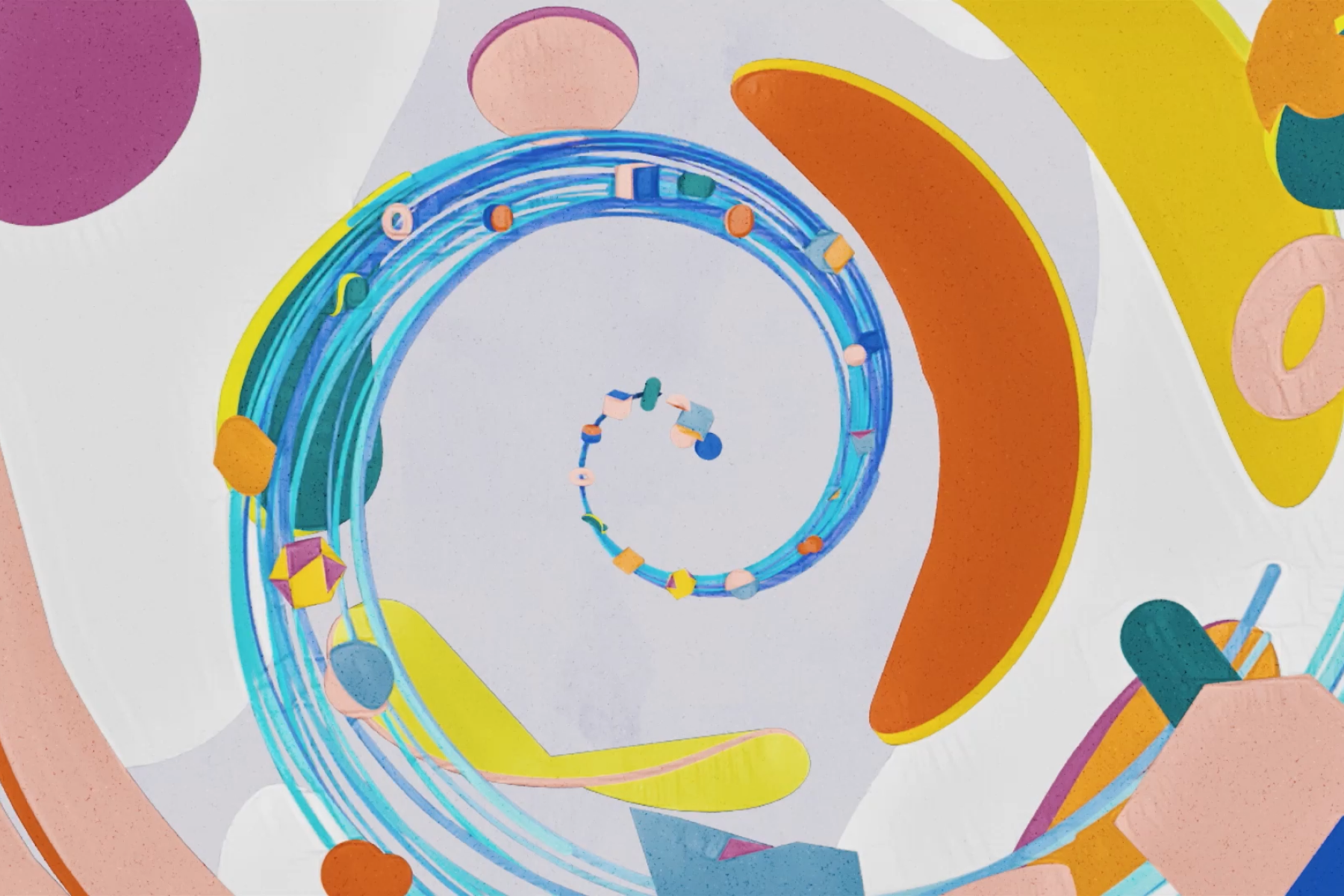
水道哲学とは、水道水のように物資を世の中に安くあまねく行き渡らせることで貧困をなくすのが企業の使命である、という経営哲学です。現代で言えば、モノはたくさんあっても、地球に優しいエネルギーや人々の生きがい、自然と生まれる思いやりが、もっと世の中にあまねく行き渡るようにすること、と言い換えられます。
パナソニックという会社が生まれた根本の考え方を、現代の社会課題に照らし合わせると、それは「共助の水道」をつくることである。そんなストーリーテリングによって、パナソニックが共助社会というビジョンを掲げる必然性が補強され、わくわくしながら未来を想像させられるようなムービーが完成しました。

発表時には、メディアや社内外からも大きな反響があったとのこと。パナソニックらしさをコアに据えながら、新しいビジョンを世の中に打ち出していくことに成功しました。
- ムービー制作 : EDP graphic works
